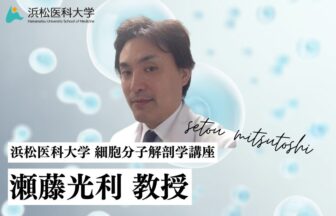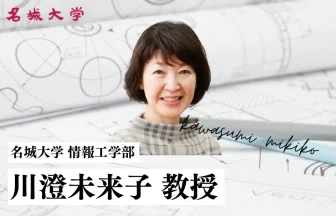崇城大学 工学部 ナノサイエンス学科 黒岩敬太教授に、専攻とされている分子組織化学を中心にインタビューを行いました。分子組織化学に関して学びを深めたいと考えている方や、黒岩敬太教授と同じ学問を専攻としていきたい学生さんは、ぜひ最後までご覧ください。
黒岩敬太教授のプロフィール

九州大学大学院工学研究院応用化学部門にて助手・助教として、一次元遷移金属錯体に関する研究に従事した(2001〜2010)。その間、カルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)バイオエンジニアリング学科にて、訪問助教として両親媒性ポリペプチドの合成に従事した(2009)、その後、崇城大学工学部ナノサイエンス学科、准教授(2012-2016)、教授(2016〜現在)として、動植物由来の両親媒性化合物に関する研究に従事している。2025年度より工学部長。博士(工学)(九州大学)。専門は、分子組織化学、高分子錯体。高分子学会代議員、編集委員、九州支部幹事、その他学会委員を歴任。日本化学会優秀講演賞、高分子学会研究奨励賞など受賞。
ご経歴と専攻分野
九州大学では、応用物質化学科(現 物質科学工学科)、大学院では物質創造工学専攻に所属していました。修士課程、博士後期課程から有機無機ハイブリッド材料の開発を研究し、その技術として一貫して分子組織化学の研究を行っています。分子組織化学が関わるものとしては、化粧品や洗剤、食品で用いられている界面活性剤が一番わかり易いですが、人間を含む生体内でも、DNAやタンパク質、脂質といったものはすべて、両親媒性化合物からなる分子組織化学の学問が根底にあります。現在も、動植物由来の両親媒性化合物(界面活性剤)を抽出したり、改変したりして、新たな触媒活性や、電子物性、さらには生理活性などを見出す研究を行っています。
教育では、高分子化学を中心として講義科目を担当しており、それらから派生する分子組織化学を教授しています。
分子組織化学を選んだきっかけ
多くの工学部がそうであるように、学部4年生になるときに研究室配属が専門分野を決定するきっかけとなりました。私が所属研究室を選んだ理由は、高分子化学を担当されていた國武豊喜教授(九州大学名誉教授、文化勲章、文化功労者、紫綬褒章など)の講義が大変面白かったことがきっかけです。特に雑談が大変面白かったです。例えば、高分子材料が人間の触覚に関連していること(すなわち現在の感性工学)を基礎化学の中で雑談されており、材料と生命現象とのつながりを身近に感じられた講義でした。そこに飛び込んでみたいと思ったのがきっかけです。そもそも、子供の頃から、私自身は自分の意思で動くロボット(トランスフォーマーやマシンロボ、ゴールドライタンなど)に興味があり、人工材料が自分の意思を持つことが出来るのかということを常日頃から考えていました。本専門分野を学ぶことはこの問いに近づけるような気がしたというのも、この分子組織化学の学問に飛び込んだきっかけであります。

様々な材料に用いることが出来る両親媒性化合物の研究(大学の広報チラシにて)
分子組織化学の主な実績
九州大学時代の恩師である國武豊喜教授、その後研究室を引き継がれた君塚信夫教授との主な業績は、一次元金属錯体の可溶化ということになるかと思います。これは、本来固体結晶中でしか存在しない無機錯体結晶を、両親媒性化合物や脂溶性化合物を用いることで、一次元状に配列したまま取り出すことが可能になりました。これは、金属錯体ファイバーのさきがけ的な研究で、金属錯体によるヒートセットゲル(あたためると固まるゲル)、磁性が変化するゲルなどが作成できました。
その後、カルフォルニア大学の恩師であるDeming教授のもとや、独自で立ち上げたこととしては、動植物由来の両親媒性化合物を合成し、それらに機能を付与するという技術です。特にトマトの葉茎由来の界面活性剤は、ナノチューブやナノシートを形成でき、それらががん細胞に取り込まれやすい条件が見出されました。このことを利用して、殺がん細胞効果をもたらすことも発見しました。
このように、世界に先駆けて両親媒性化合物の応用技術をいくつか発表できたことが主な業績です。

キヤノン財団研究助成における助成金贈呈式(2017年4月)
分子組織化学から日々の生活に活かせること
私達の専門分野である分子組織化学は、恩師である國武豊喜教授が1977年に発表したところから世界的に影響を与えた研究です。現在では、高分子化学や有機化学だけではなく、生化学、電子工学、物理化学、錯体化学、無機化学、分析化学などのありとあらゆる化学の応用技術として波及しています。よって、身近な化粧品工学や洗浄剤工学、食品工学、あるいは工場の洗浄・潤滑剤に応用されているだけでなく、医療材料、薬品材料にも応用されています。このことは、日々のわかりやすい化学が最先端材料を担っている例でありますので、高大連携活動などでも大いに活用できる内容となっています。言い換えれば、身近な化学は両親媒性化合物を用いた分子組織化学なくしては成り立たないといっても過言ではありません。
現在では、これらの身近な日用品だけでなく、量子化学に利用するためのボトムアップ材料や、AIを用いた情報工学や機械学習との接点などでも議論されており、最先端材料を担う材料になっていくと考えられています。これらの最先端材料に従事できていることは、非常に楽しく、日々新鮮さを感じながら研究を推進しています。

崇城大学での高大連携企画 市民公開セミナーと高校生による探究研究の発表会主催
分子組織化学に関心のある方へのアドバイス
この研究分野は、現在の化学の発展を牽引してきたと言っても過言でない分野です。そのためには、日々から新しいことを考え続けることが重要で、0を1にしたいと考える人が向いている分野であると思います。あるいは様々な視点をめぐらして、人とは違う新しい概念を提出できるような人は向いています。化学・物理・生物などの学際的な視点はもちろんなこと、情報科学や経済、感性やデザインといったことも今後は絡んでくると考えられます。よって、工学という分野ではありますが、研究開発だけでなく、文系理系問わず様々な学問が融合していくことで、新しい学術分野が生まれてくる基盤分野であると思います。
私自身も、工学の応用化学という分野だけでなく、医学や薬学、感性工学や経済学など、多くの分野を学び直すことをこの歳からも始めています。そして、様々な企業や大学、地方自治体との共同研究が開始され始めています。このようにして人の役に立つ材料開発に繋げられていると感じています。
みなさんも、新しいことを考え続けられる意識を常日頃から養ってみませんか?面白いアイデアが学術の根底を変える日が来るかもしれません。